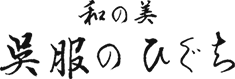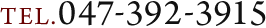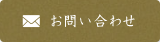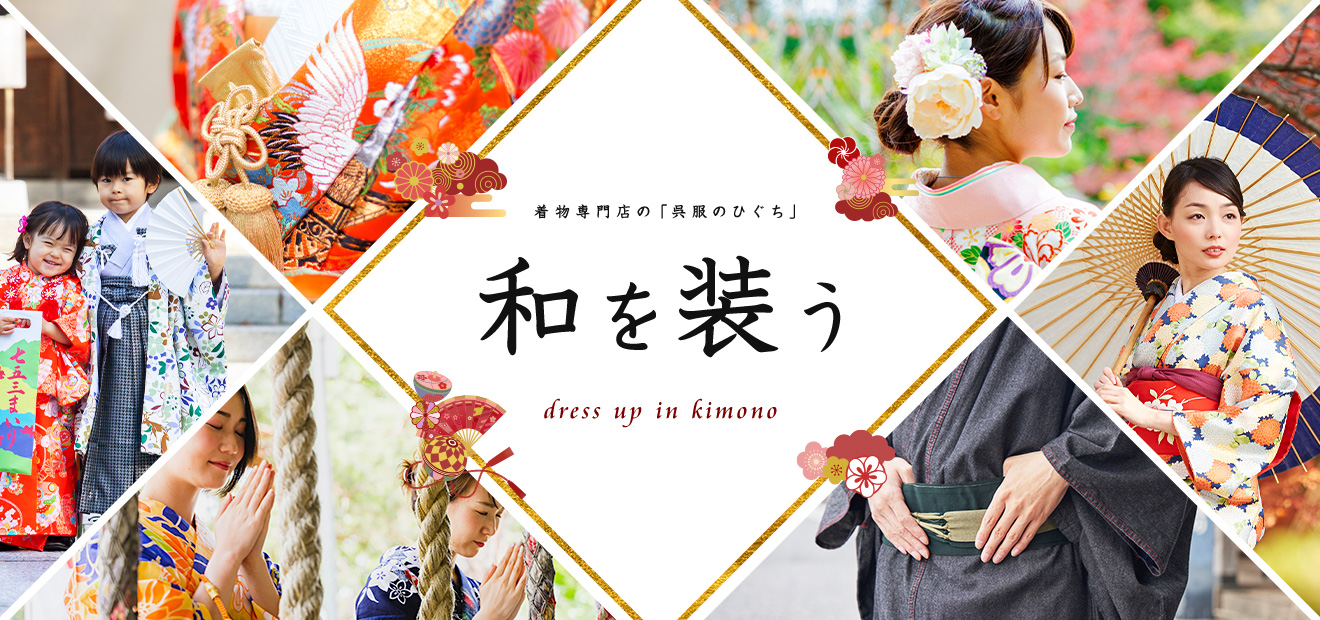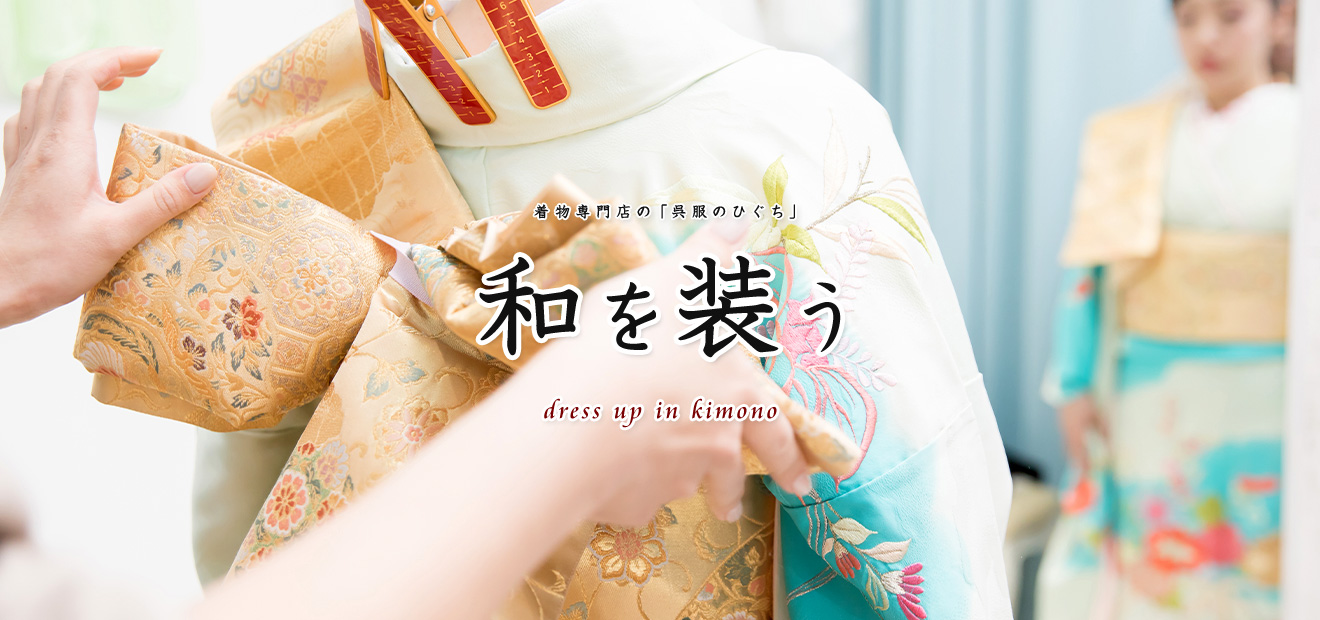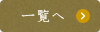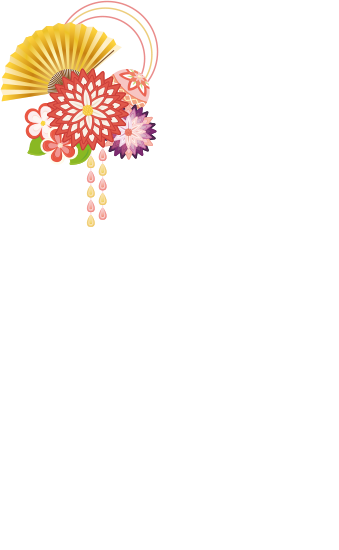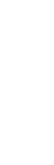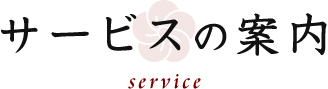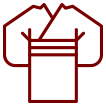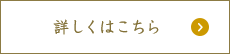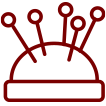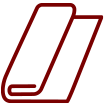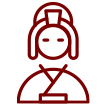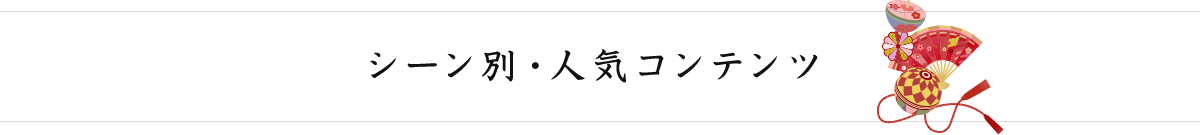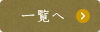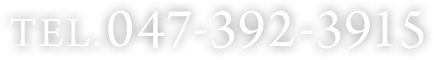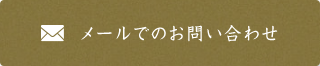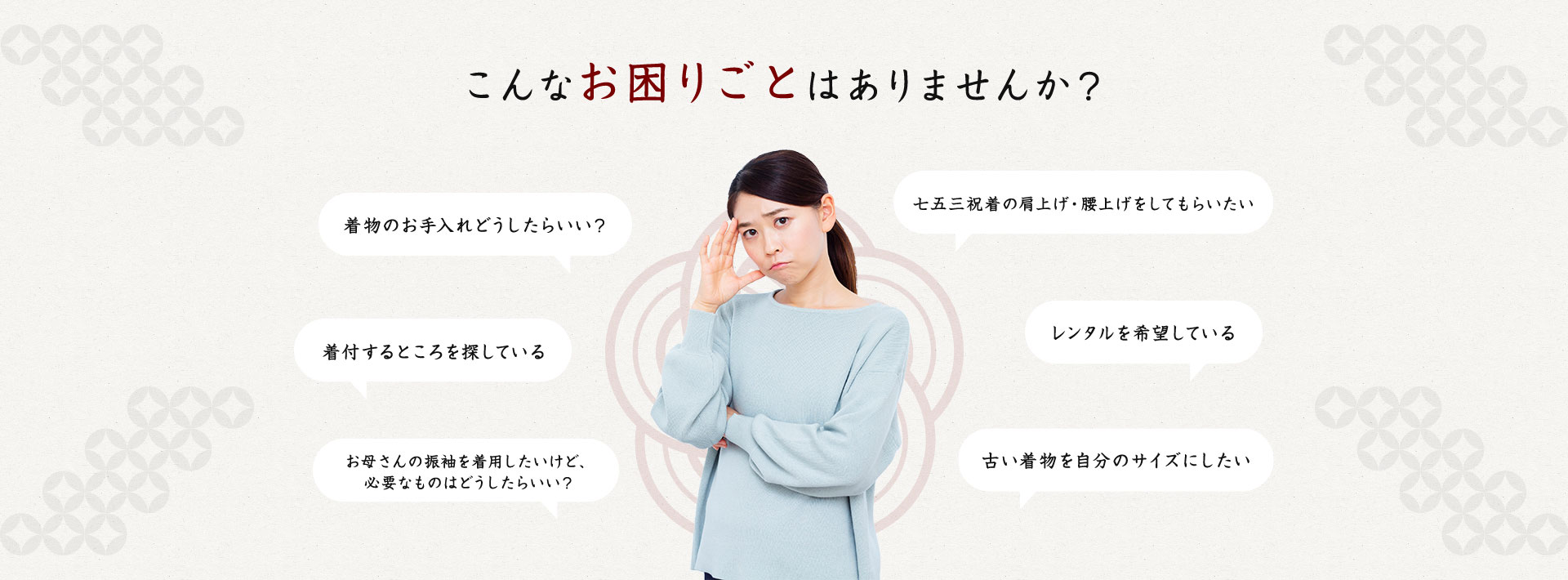
-
着物レンタル

-
着物お手入れ

-
取扱い商品

-
着付け

-
2023.07.24 留袖を日傘にリメイク(リフォーム)
-
2023.06.05 男児お宮参り祝着の家紋入れ替え
-
2023.05.11 注染本染め 子供浴衣 入荷しました
-
2023.01.09 二十歳の成人式 男袴姿 記念写真撮影
-
2022.11.28 留袖のカビ落とし